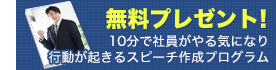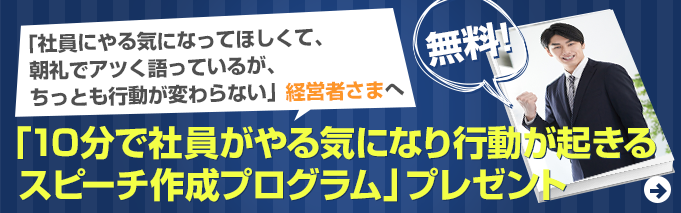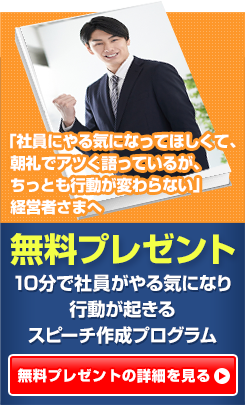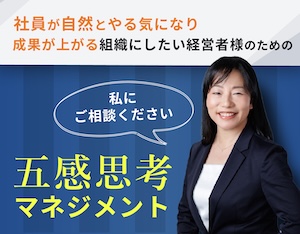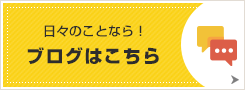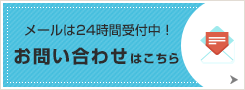国宝に学ぶ「成果は個人ではなくシステムで生まれる」
【五感思考day2618】
こんにちは!
人が自立的に動き、グングン成果が出る仕組みをつくる
組織づくりコンサルタントの大図美由紀です^ ^
本日もブログをお読みいただき、
ありがとうございます。

先日、映画『国宝』を観てきました。
上映時間が3時間と長く、「耐えられるか」とちょっと躊躇してましたが、、、
観に行って正解!
深く考えさせられる時間になりました。
歌舞伎という伝統の世界を舞台に、多くの人の努力と関わりが積み重なって「芸」が受け継がれていく姿は、経営や組織づくりに通じるものが多くありました。
腑に落ちない点もあったので、原作小説も手に取り、改めて物語に触れてみました。
本日は、小説も含めて、一部ネタバレありの内容です。
主人公の喜久雄は任侠の家に生まれますが、歌舞伎の名門当主・花井半二郎に才能を見出され、引き取られます。
そして、花井の跡取り息子・俊介と兄弟のように育てられ、親友でありライバルでもあり、互いに芸を磨き高め合い、国宝へ――そんな物語です。
2人の姿から見えてくるのは、天性の才能があっても、また名門の家柄があっても、それだけでは道を切り拓けないという現実です。
喜久雄も俊介も、数々の不遇や挫折に見舞われます。
しかし、彼らが再び表舞台に立つことができたのは、才能や血筋ではなく、周囲の支えがあってこそでした。
天才的な資質があったとしても、それを導いてくれる師匠や仲間、舞台を支える裏方、そして観客がいて初めて、「国宝」と呼ばれるまでになりました。
私はその構造を見ながら「これは事業の承継や組織経営そのものだ」と強く感じました。
成功要因その1は、「諦めない覚悟」です。
俊介はボンボン気質ゆえに伸び悩み、一度は逃げ出します。
けれど、地方巡業を重ねる中で覚悟が決まったところで、芸が磨かれ、歌舞伎界の重鎮の眼鏡にかない、再び舞台へ。
そこから大きく飛躍していきます。
人は、覚悟が決まった人を、応援したくなります。
また、この「諦めない覚悟」は役者だけでなく、女将や興行主といった裏方にも共通します。
彼らもさまざまな苦境に立たされながらも、必死に歌舞伎界を支え続けるのです。
成功要因その2は、「ご縁を大切にすること」です。
喜久雄は、花井半二郎の死で後ろ盾を失い、芸があっても役を得られなくなります。
そこで、別の歌舞伎名門の娘と結婚して役を得ようとしますが、それは見透かされ、逆に歌舞伎界から勘当されてしまいます。
ところがその後、任侠つながりの恩人のために、役者生命を失いかねない状況にもかかわらず、踊ったことで、「縁を大切にする人」と認められ、後ろ盾を得て表舞台に戻ることができるのです。
人は、利用する人ではなく、周りの人を大切にする人の力になりたいものです。
こうして、主要人物たちが「諦めない覚悟」と「ご縁を大切にすること」を持ち続けた結果、国宝を生み出し、事業としても成功し、伝統が引き継がれていく。
つまり、リーダーはモチロンですが、関わる人たちが、素晴らしい歌舞伎を繋いでいくという同じ方向性の中で、それぞれの仕事に責任を持ち、お互いに協力し合ったからこそ、できたこと。
多くの人がそれぞれの役割を果たし合うシステム全体こそが「成果」を生み出していたのです。
これは、まさに組織づくりにも当てはまります。
突出した一人(多くの場合は経営者でしょうか)の能力だけの会社は、長く続きません。
持続的に成果を上げる企業は、同じ目的に向かって、社員一人ひとりが役割を果たし、互いに補い合い、世代を超えて受け継がれていく「文化や仕組み」を持っています。
映画のタイトルである「国宝」は、個人の栄誉であると同時に、その人を支えた環境や仕組みの証でもあるのだと思いました。
もう一段飛躍したい、社員の力をもっと生かしたい――そんな経営者の皆さまを、応援しています!
本日の問いかけ御社にとっての国宝(成功)は何ですか?成功を次世代に引き継いでいく文化や仕組みはありますか?